
カストロールといえばクルマ好きなら誰もが知っている、世界最大手の潤滑油メーカー。
そんなカストロールがオイルについてのレクチャーをしてくれて、元レーシングドライバー鈴木亜久里氏のトークショーまであり、しかもバーチャルサーキットの試乗会まであるという豪華絢爛なイベントを開催してくれるというのです。
そんなイベントに当たったらいいなと思っていましたが、まさか本当に当選するなんて。
という事で、カストロール エッジ オイルマイスタープロジェクトに参加してきました。
何でバーチャルサーキット?と言うと、現在カストロールは「カストロール エッジ 最強チタンの挑戦 "クローンライバル" − ケーニヒゼグ」というプロモーションをやっており、バーチャルを現実に体験できる施設としてここ東京バーチャルサーキットを選んだとの事でした。
YOUTUBE URL:https://www.youtube.com/watch?v=s2spxW53Io0
※なお、このブログの内容は私の記憶とメモを元にしていますので完全には正しくない恐れがあります。
このブログの内容に関してBPカストロール株式会社へ問い合わせる事はおやめ下さい。
-施設情報-
所 在 地: 東京都 港区 赤坂 6-6-19 メゾン・ド・ヴィレ1F
電話番号 :03-6277-6354
ホームページURL:http://tokyovirtualcircuit.jp/
写真1

カストロールのノボリが立っていたおかげで無事に東京バーチャルサーキットへ入ることができました。
東京バーチャルサーキットって何?
東京バーチャルサーキットとは、世界では当たり前になりつつあるレーシングマシンのシミュレータを備えた施設で、一般車両からレーシングカーまでいろいろな車両で、また色々なサーキットを走ることができるというハイテク施設なのです。
ゲームと何が違うの?と思っていましたが、ゲームで必要な面白さを排除してリアルを追及しているためにレーシングドライバーも納得のリアリティを実現しているとの事。
最近は実際のマシンセッティングなどもバーチャルサーキットで行うそうです。
そんなスペシャルな施設ですが、我々一般人も使用可能。
URL:http://tokyovirtualcircuit.jp/
写真2
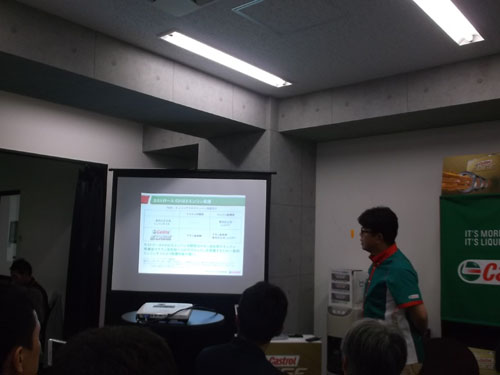
まずはカストロールのエンジンオイル、エッジはどんな所が優れているのか?というレクチャーから。
講師はBPカストロールの大橋氏。
新しいカストロール・エッジと言うと液体チタンによる保護性能アップが売り文句になっています。
液体チタンとは何者か?
簡単に言うと摩耗低減剤の一つらしいです。
既存の一般的な摩耗低減系添加材は温度が60度以上になると化学反応により摩耗低減効果を発揮するのですが、60度以上になるまではこの添加剤の恩恵を得られません。
しかし液体チタンは25度からその摩耗低減効果を発揮するため、エンジン始動時の摩耗をより抑える事ができるとの事でした。
つまり今のように暑い時期であれば、エンジンを始動した時点で既存のエンジンオイルよりも高い保護性能を発揮しているという事なのですね。
しかしカストロール・エッジ最大の売りは液体チタンではなく、あくまで先代カストロール・エッジ(円っぽいデザインの描かれた缶)で実現しているエンジンオイル自体が持つ「歴代最強の保護皮膜」なのだそうです。
あくまで添加材は低温時の保護性能を補助するものとの事でした。
液体チタンという珍しい添加剤ばかりに目が行きがちですが、基本となるエンジンオイルにこそ絶対の自信があるようです。
写真3

非常に濃いオイルレクチャーの次は、プロフェッショナルレーシングチームARTA監督であり元レーシングドライバーの鈴木亜久里氏のトークショーです。
実は鈴木亜久里氏は既にこのバーチャルサーキットを走った事があるそうですが、「事故っても痛くないから」と無茶な走行でスピンしたそうで。
速くなるためには?との質問には「とにかく練習あるのみ」だそうです。
練習していけばとっさの出来事にも対応できるようになりますし、走っていて何が起きるか予感できるようになるとの事でした。
とにかく、基本が何よりも大事なんだそうです。
クルマのチューニングよりも、とにかく走り込む事。
最近のクルマはノーマルでも十分サーキットを走れるものもあるので、昔に比べてクルマにかけるお金は少なくなってきているそうです。
「どれだけクラッシュしてもマシンや部品代のかからない、ここバーチャルサーキットは練習用として大変にイイ」のだとか。
今はプロフェッショナルのレーシングドライバーもバーチャルマシンで練習する時代だそうです。
カストロールとの出会いは?
カストロールとの出会いは、鈴木亜久里氏が最初に乗っていたカートのエンジンオイル。
当時はまだひまし油だったそうですが、同じひまし油のベースオイルでもカストロールのオイルは焼きつかなかったそうで。
その後はチームによって使うオイルは違ったものの、今はカストロールを採用しているとの事です。
「今のオイルは高性能だから、レーシングマシンにはオートバックスでカストロール・エッジを買ってきてオイル入れてる」なんて冗談を飛ばす場面も。
(オートバックス店舗に買いに行くのは冗談だと思いますが、実際市販と同じエンジンオイルを使用しているらしい)
その後は質疑応答
Q:「あるサーキットのある場所が怖いのですが、どうやったら克服できますか?」
A:「怖いと思うなら今はそこが限界だから、今はそれ以上頑張ったらダメ。練習していくと克服できるようになる」
Q:「こんなオイルがあったら良いというものはありますか?」
A:「使っていてオイルの心配をしなくて良いオイルが良い。そうしたら他の事を考えられるから。その点カストロールさんは良い仕事をしてくれている」
Q:「レーシングドライバーに必要な適性は?」
A:「臆病な事かな。臆病だからマシンのコンディションが気にかかるし、走りも無茶をしない」
最後には「エンジンオイルを買うなら、オートバックスでカストロール・エッジを買ってね」とお決まりの締めでトークショーは終了。
その後は記念撮影とツーショット写真をして、握手までしてくれました。
これは嬉しい。
写真4

さて、ここは東京バーチャルサーキット。
世界中の様々なサーキットを様々な車両で走行できる訓練施設です。
体験走行という事で、まずは箱車からトライ。
中身はMX-5、マツダ・ロードスターとなっています。
走っているのは富士スピードウェイ。
こちらではシミュレータの勝手がわからずスピンしたりペースアップできなかったりと散々でした。
でもサーキット走るのって楽しいね。
写真5

お次はフォーミュラマシン。
ダウンフォースを高め、走りやすい特性にしてくれているとの事です。
フォーミュラマシンのタイヤグリップってこんなにあるのか!と驚きながらも、大変にマシンが扱いやすいので順調に走ります。
しかし、これで速さを求めてダウンフォースを減らしてゆくとジャジャ馬ぶりを発揮するのでしょう。
こちらは頭にある富士スピードウェイのマップと、先ほどのロードスターでシミュレータに慣れてきたおかげで割とマトモに走ることができました。
担当の方から「ブレーキいいよ」と褒められたのは、正直嬉しい。
これは…サーキットでブレーキの練習ですね(笑
その後は元レーシングドライバー砂子塾長からのインストラクション。
サーキットで大事なのはコーナリング。
「でもコーナリングの適正速度は物理的に上限があるから、60キロのコーナーを61キロで抜けてしまうとタイムダウンになる」
タイヤのグリップは100%以上発揮されない完全に物理の世界なので、タイヤグリップが200%になるようなミラクルは起きない。
そのコーナーを曲がれるタイヤの限界を100%完璧に見極めて走るのがレーシングドライバーの仕事なんだそうです。
特に加速はエンジンとタイヤの仕事でドライバースキルは一切関係ないので、とにかく加速をさせるためのコーナリングスピード見極めが大事。
それさえできれば、素人でもプロと同じ加速ができるそうです。
これは60キロのコーナーを61キロで曲がろうとひたすら頑張っていた私には目から鱗でした。
またデータロガーのグラフも参照しながら、良いグラフや悪いグラフの見方も教えていただきました。
「車は違えど同じコースなら同じ操作」という、大変に大事なことも教えていただきました。
さて…。
ここからが本番。
世界最大手のオイルメーカー、カストロールのオイルマスター大橋氏へのオイル質疑応答です。
常識や定説とされている事は、実際正しいのか?
そんな疑問を本家本元、カストロールにオイルについての質問をぶつける大チャンス。
ここを逃す訳にはいきませんよ!
私だけではなく、他の質問も載せています。
さすがクルマを愛する皆さんだけあって、質問が矢のように飛んでいました。
Q:「世界的に見ると、オイルの低粘度化はどうなっているのか?」
A:「低粘度化については日本が一番進んでいる。ホンダが0W-8を採用しており、トヨタが0W-16を採用しているが、海外ではようやく0W-20の採用の車両が出始めてきている程度。日本の低粘度化は非常に進んでいる」
Q:「エンジンオイルの交換時期はどう見極めるのか?」
A:「色で判断するのは良くない。
色で判断してしまうと、ディーゼルエンジンのオイルは毎日交換することになる。
いわゆるシビアコンディションで使用しているなら、距離を走っていなくても例えば6カ月に一回といった感じで期間で交換するのが良い。
ターボの場合はNAエンジンの半分の期間で交換することが望ましいが、これらは自動車の取扱説明書に記載してあるので参照して欲しい。」
「一番良い交換頻度は、交換しても劣化を感じない頻度。
劣化を感じるという事はそれだけエンジンオイルの性能が劣化しているから。
同じオイルを使用し続け、車両ごとのタイミングを見極めるのが一番良い」
Q:「走行距離が伸びてきた場合、エンジンオイル粘度は増やした方が良いのか?」
A:「個体差はあるが走行距離がおおよそ10万キロを超えた場合、エンジンオイル粘度は一つ上げたほうが好ましい。
0W-20を採用している車両であれば0W-30や5W-30への変更でエンジンライフを伸ばしたりエンジンの静粛性を回復することが期待できる。」
Q:「エンジンオイルの使用期間は?」
A:「封を切っていなければ冷暗所保管で2年は大丈夫。
封を開けた場合、蓋を閉め冷暗所で保管すればその後1年は大丈夫。
その際、できるだけ量が多い方が良い。
大気に触れているとすぐにダメになるので、必ず密閉する事。
水が入ってもダメ」
Q:「EDGE同士のブレンドで粘度調整はできるか?」
A:「やらない方が良い。
例えば5W-40と5W-50オイルを混ぜて5W-45にしようと思っても、粘度指数向上剤が悪さをして5W-30になる可能性がある。
粘度低下はエンジン保護にとって致命的。」
(例であって実際にそうなる訳ではないようです。しかしブレンドはお勧めできないとの事)
という事で、内容盛りだくさんで大満足のオイルマイスタープロジェクトでした。
何度も「粘度」という言葉が出てきますが、過去にあるオイルメーカー(カストロールではない)に問い合わせた時と同じ意味でした。
つまり、「エンジンオイルを選ぶときには規格よりも粘度を重視してほしい」と。
それほどにエンジン保護にはエンジンオイル粘度が大事なんですね。